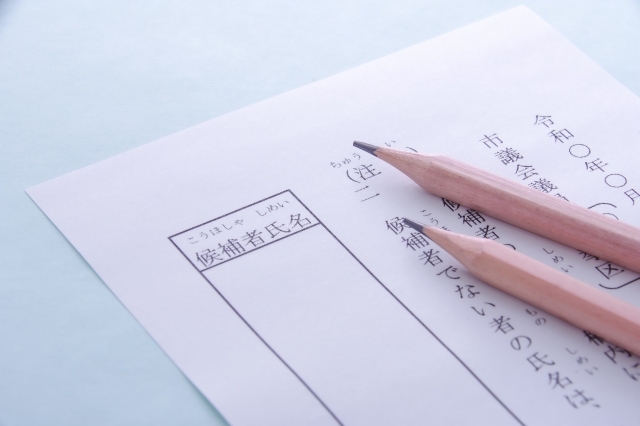昨年10月に行なわれた衆議院選挙のいわゆる「一票の格差」をめぐる裁判で、今月に入って6件高等裁判所で判決が言い渡されました。
判決が出たのは広島、大阪、札幌、東京での裁判でいずれも「合憲」と判断され、原告の弁護士グループらが訴えた選挙のやり直しは退けられることになりました。
最大2.06倍となった2024年衆院選の「一票の格差」。今回の判決はどう受け止めればいいのでしょうか?
2月18日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、光山雄一朗アナウンサーがこのニュースについて、アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士に尋ねます。
「一票の格差」とは
いわゆる「一票の格差」について解説する正木弁護士。
正木「選挙区ごとに議員ひとり当たりの有権者数が違うために、一票の価値や重みに不平等が生じている状態のことを言います。
憲法では平等が重視されているので、ひとりひとりの一票の価値は平等でなくてはならない。だからこそ性別、身分、財産、教育などで差別しないで、ひとりが一票を投票できるという選挙制度を設けています。
愛知一区、二区、三区といった小選挙区がいろいろ設けられていますが、区によって有権者数が異なります。例えばA選挙区では有権者数が10人、B選挙区では100人いるという場合、A選挙区の方が一票当たりの価値が高くなり、B地区は価値が低くなり、意見が反映されにくく、平等に反するのではないかということが争われるわけです」
正木「選挙区ごとに議員ひとり当たりの有権者数が違うために、一票の価値や重みに不平等が生じている状態のことを言います。
憲法では平等が重視されているので、ひとりひとりの一票の価値は平等でなくてはならない。だからこそ性別、身分、財産、教育などで差別しないで、ひとりが一票を投票できるという選挙制度を設けています。
愛知一区、二区、三区といった小選挙区がいろいろ設けられていますが、区によって有権者数が異なります。例えばA選挙区では有権者数が10人、B選挙区では100人いるという場合、A選挙区の方が一票当たりの価値が高くなり、B地区は価値が低くなり、意見が反映されにくく、平等に反するのではないかということが争われるわけです」
10月の衆院選の一票の価値
今回の訴訟の経緯について尋ねます。
正木「昨年10月の衆院選について争われているんですが、投開票日時点で有権者数がもっとも多かった北海道三区、これがもっとも少なかった鳥取一区と比較して、有権者数は約2.6倍だった。
つまり、一票の価値が0.49票分しかなかった。
そういう状況なので、選挙は憲法違反だからやり直せということで争われている裁判になります」
違憲となった例はありますか?
正木「何度もあります。最初は1972年。このときは格差が約5倍でした。これに関して最初に違憲判決が出ています。その後も4倍台のときも出ていますし、違憲ではなくても違憲状態、このまま放っておくと違憲という判断にしますよ、というものが何度も出ています」
正木「昨年10月の衆院選について争われているんですが、投開票日時点で有権者数がもっとも多かった北海道三区、これがもっとも少なかった鳥取一区と比較して、有権者数は約2.6倍だった。
つまり、一票の価値が0.49票分しかなかった。
そういう状況なので、選挙は憲法違反だからやり直せということで争われている裁判になります」
違憲となった例はありますか?
正木「何度もあります。最初は1972年。このときは格差が約5倍でした。これに関して最初に違憲判決が出ています。その後も4倍台のときも出ていますし、違憲ではなくても違憲状態、このまま放っておくと違憲という判断にしますよ、というものが何度も出ています」
かつては3倍未満なら大丈夫
何倍というのがポイントになりますか?
正木「これは非常に大きいです。衆院選の小選挙区の場合、2005年頃までは4倍を超えると違憲と出ていた。3倍台だと違憲状態。2倍台までは合憲という判断が出されていました。
5倍のときに違憲と出たので、いろいろ制度が変えられて下がってはきましたが、3倍を切れば違憲はでないという状態だったので、抜本的な改革までなかなか立法府は踏み込まなかった。3倍未満なら大丈夫という状況が続いていました」
ところが2014年12月、最大格差が2.13倍で最高裁が違憲状態という厳しい判決を出し,選挙制度の改革が進むことになりました。
正木「立法府に早く改正しなさいと圧をかけたということになります。
これによって選挙制度改革関連法案というものが成立して、区割りが変わっていくという形が進みました。その改正があったため、その後、2017年の選挙は最大格差1.98倍で合憲。
2021年は最大格差2.08倍ではあったのですが、新しい選挙制度については合理的だと判断して、今回は合憲にしましょうという判断が出ています」
正木「これは非常に大きいです。衆院選の小選挙区の場合、2005年頃までは4倍を超えると違憲と出ていた。3倍台だと違憲状態。2倍台までは合憲という判断が出されていました。
5倍のときに違憲と出たので、いろいろ制度が変えられて下がってはきましたが、3倍を切れば違憲はでないという状態だったので、抜本的な改革までなかなか立法府は踏み込まなかった。3倍未満なら大丈夫という状況が続いていました」
ところが2014年12月、最大格差が2.13倍で最高裁が違憲状態という厳しい判決を出し,選挙制度の改革が進むことになりました。
正木「立法府に早く改正しなさいと圧をかけたということになります。
これによって選挙制度改革関連法案というものが成立して、区割りが変わっていくという形が進みました。その改正があったため、その後、2017年の選挙は最大格差1.98倍で合憲。
2021年は最大格差2.08倍ではあったのですが、新しい選挙制度については合理的だと判断して、今回は合憲にしましょうという判断が出ています」
アダムズ方式とは?
今回、2.06倍となった2024年の衆議院選の「一票の格差」に関しては,4か所の高裁が合憲と判断しています。
その判断でポイントとなるという「アダムズ方式」について解説する正木弁護士。
正木「簡単にいうと、人口に応じて小選挙区を各都道府県に分配することによって、人口比が区割りに反映しやすくなる。それによって最大格差が2倍未満となるような方式です。
10年の国勢調査をもとに人口を調べ、それによって区割りを変えていくということで、たとえ格差が増えてしまっても、将来的に是正される見込みとなるために、これは合理的な方式だと最高裁も評価しています。
今回の高裁もこのアダムズ方式については合理的であることは変わらない。今回、この方式で2倍を超えたところはあるが、予期しない人口移動によるもので、それ以上の要因があったというわけではないので、今回合憲だという形で判断しています」
その判断でポイントとなるという「アダムズ方式」について解説する正木弁護士。
正木「簡単にいうと、人口に応じて小選挙区を各都道府県に分配することによって、人口比が区割りに反映しやすくなる。それによって最大格差が2倍未満となるような方式です。
10年の国勢調査をもとに人口を調べ、それによって区割りを変えていくということで、たとえ格差が増えてしまっても、将来的に是正される見込みとなるために、これは合理的な方式だと最高裁も評価しています。
今回の高裁もこのアダムズ方式については合理的であることは変わらない。今回、この方式で2倍を超えたところはあるが、予期しない人口移動によるもので、それ以上の要因があったというわけではないので、今回合憲だという形で判断しています」
今回は合憲となるか?
今後この裁判はどうなっていくのでしょうか?
正木「おそらく3月7日の福岡高裁が今回の裁判の最後の判決になるので、それを待ってから最高裁が統一判断を示すと思われます」
この最高裁の判断はどうなりそうでしょうか?
正木「2倍というのがとても大きな壁になりますが、アダムズ方式が前回も大きく評価されています。今回2倍を超えましたが、前回の2.08倍のときも最大格差が極めて大きいわけではないと最高裁は言っています。そうすると今回、2.08より少ないことを考えると合憲、いったとしても違憲状態という形が出ると思われます。これは個人的な意見です」
正木「おそらく3月7日の福岡高裁が今回の裁判の最後の判決になるので、それを待ってから最高裁が統一判断を示すと思われます」
この最高裁の判断はどうなりそうでしょうか?
正木「2倍というのがとても大きな壁になりますが、アダムズ方式が前回も大きく評価されています。今回2倍を超えましたが、前回の2.08倍のときも最大格差が極めて大きいわけではないと最高裁は言っています。そうすると今回、2.08より少ないことを考えると合憲、いったとしても違憲状態という形が出ると思われます。これは個人的な意見です」
1倍に近づける努力
「一票の格差」についての考えを最後にまとめた正木弁護士。
正木「16年に退官された裁判官が『この裁判は司法と立法府のキャッチボール』と言っています。
司法が違憲状態だということで、立法府は問題だと改正をしていく、それによって一票の価値が平等になるように制度をどんどん変えていく、キャッチボールは続いていくと評価されています。
民意を正確に反映するためには、できるだけ1倍に近づけなければいけない。2倍を超えてないからOKというものではない。たゆまぬ努力が必要になってきます。
これからも多様な生き方が進むので、いろいろなことが変わってきます。消滅可能性自治体もある中でこれからの社会は大きく変わるので、1倍を超える状態がおかしいと声をあげ続けることが我々を守ることにつながるので、ぜひみなさんも注視していただきたいと思います」
(みず)
正木「16年に退官された裁判官が『この裁判は司法と立法府のキャッチボール』と言っています。
司法が違憲状態だということで、立法府は問題だと改正をしていく、それによって一票の価値が平等になるように制度をどんどん変えていく、キャッチボールは続いていくと評価されています。
民意を正確に反映するためには、できるだけ1倍に近づけなければいけない。2倍を超えてないからOKというものではない。たゆまぬ努力が必要になってきます。
これからも多様な生き方が進むので、いろいろなことが変わってきます。消滅可能性自治体もある中でこれからの社会は大きく変わるので、1倍を超える状態がおかしいと声をあげ続けることが我々を守ることにつながるので、ぜひみなさんも注視していただきたいと思います」
(みず)
関連記事